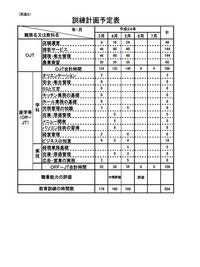› 仕事は芸術だ! › 会社は会話の中に
› 仕事は芸術だ! › 会社は会話の中に2005年09月01日
会社は会話の中に
ビジネス・コーチへの道① -2-
「小さなチームは組織を変える」-ネイティブ・コーチ10の法則― 伊藤守著
の中から10の法則を毎回ひとつひとつ自分に置き換えながら考えていくシリーズ。

若干、哲学的な法則である。深く考えると個人にも当てはまる法則でもある。
会社が2、3人程度で資産を持たない創業期を想像してみると解りやすい。これから、どんな商品、サービスを提供していくか?その答えは社内の会話の中に存在する。お互いの知識や経験、技術を提供しあう中に、互いの役割を理解し行動する中に、お互いの仕事をフィードバックし合い行動を修正する中に、互いが学習し合う中に。すべてコミュニケーションの中に存在する。これは社内に限らず、取引先、顧客との間にも、又は他人同士の話題の中にも存在する。
「小さなチームは組織を変える」-ネイティブ・コーチ10の法則― 伊藤守著
の中から10の法則を毎回ひとつひとつ自分に置き換えながら考えていくシリーズ。

若干、哲学的な法則である。深く考えると個人にも当てはまる法則でもある。
会社が2、3人程度で資産を持たない創業期を想像してみると解りやすい。これから、どんな商品、サービスを提供していくか?その答えは社内の会話の中に存在する。お互いの知識や経験、技術を提供しあう中に、互いの役割を理解し行動する中に、お互いの仕事をフィードバックし合い行動を修正する中に、互いが学習し合う中に。すべてコミュニケーションの中に存在する。これは社内に限らず、取引先、顧客との間にも、又は他人同士の話題の中にも存在する。
会社がどんなに大きくなっても、その存在は無数の1:1のコミュニケーションに支えられている。ある程度の規模になると、社訓や階層システムを導入し、価値感の維持統一、指揮命令系統の効率化を図る。しかし、ただそこに社訓があるだけでは意味がない。また丸覚えしたり、連呼してみても意味がない。その社訓について社内で会話を交わし、自分なりに咀嚼し取り入れて初めて意味を持つ。各種のシステムも作り上げ育て維持改革するための会話があって機能する。
マネジャーの役割は、そんな会話ができる環境を整え、創り上げ、運営することである。そして、求められるスキルは効果的な質問を作り出すこと。仮に経費節減という命題があったとしたら、「どんなことが出来ると思いますか?あなたの考えを聞かせてください」と質問することである。
と、自分なりに咀嚼してまとめてみましたが、さて我社に当てはめてみますと・・・・。
「個別スタッフミーティング」を継続し対象を広げ会話の内容を深めること。「社内新聞」(最近始めたばかり)でスタッフ間の会話の話題を作り、ベクトルをシンクロさせること。を行っている。真価がこれから問われる。
また、発展的に「ブログ」「ホームページ」等でお店のファンを醸成し、ファンの間でお店の会話ができるような話題提供も必要になってくる。
ひとつ思うことは、「会話」を重視することは、労働集約型から知識集約型への脱皮を生み、より収益性の高い事業スタイルへの進化が期待できるであろうこと。
深い法則です。
マネジャーの役割は、そんな会話ができる環境を整え、創り上げ、運営することである。そして、求められるスキルは効果的な質問を作り出すこと。仮に経費節減という命題があったとしたら、「どんなことが出来ると思いますか?あなたの考えを聞かせてください」と質問することである。
と、自分なりに咀嚼してまとめてみましたが、さて我社に当てはめてみますと・・・・。
「個別スタッフミーティング」を継続し対象を広げ会話の内容を深めること。「社内新聞」(最近始めたばかり)でスタッフ間の会話の話題を作り、ベクトルをシンクロさせること。を行っている。真価がこれから問われる。
また、発展的に「ブログ」「ホームページ」等でお店のファンを醸成し、ファンの間でお店の会話ができるような話題提供も必要になってくる。
ひとつ思うことは、「会話」を重視することは、労働集約型から知識集約型への脱皮を生み、より収益性の高い事業スタイルへの進化が期待できるであろうこと。
深い法則です。
Posted by 茶花スタッフ at 16:42│Comments(0)