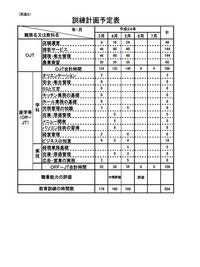› 仕事は芸術だ! › 脳の中の人生
› 仕事は芸術だ! › 脳の中の人生2007年02月26日
脳の中の人生
脳の中の人生 著)茂木健一郎
◇究極は、この上なく複雑であるとは言ってもやはり物質にすぎない脳に、いかにして「心」が宿るのかという問い。
◇疾病に即して解決への道を探る「臨床医学」があるように、一人一人の人生の中で起こった具体的な出来事に脳の視点から向き合う「臨床脳科学」があってもいい。
◇創造することは思い出すことに似ている
◇情報は外からやってくるだけでなく、自分の中から掘り起こすものでもある。
◇一度過ぎ去ったことは変える事はできないけれれど、過去の見方を変える事はできる年をとると言うことは、記憶の「編集力」を通して新たな発見をなし得る、豊かな可能性の鉱脈がそれだけ増えるということ。
◇脳も一つの生きた臓器である以上、その健康に気を配るのは当然。本を読むこと、それは一つの手入れである。
◇感情の役割は、生きていく中で直面する不確実さにうまく対応することである。
◇進化の過程で残った感情は、生きるための意味を持っている。
◇科学は、仮説を立て、それを検証することで進歩していく。
◇鏡は自分をあたかも他人であるかのように見る道具である。
◇私たちは生活の状況にあわせて少しずつ違う人格が現れる。マイルドな多重人格者とも言える。
◇不安や恐怖、嫉妬といったネガティブな気持ちも、感情のエコロジーの中で果たすべき役割があるからこそ、進化の過程で生き残った。
◇さまざまな人生経験を通じて、感情のエコロジーの多様性を耕していくことが大事。
◇外から興味深い刺激が入ってこない状態で、脳が自ら何かを作り出そうとするときに、ひらめきが訪れるらしい。
◇動物は「安全基地を確保する」という命題と「新しい可能性を探求する」という命題を両立させることで生き延びてきた。
◇人間の判断はルールでは書けない。
◇「サッカー型」の組織を維持する上では「言葉」の役割が大きい。トップが明確なメッセージを出し続けることが、個人の自発性が組織の中で生かされ、組織のパフォーマンスが上がるための条件といえる。
◇人間は他者という鏡を得てはじめて自己を磨くことが出来るし、ユニークな個性をはぐくむことも出来る。
◇言葉とは他人と自分とを結ぶ「鏡」のシステムの産物。
◇幸運は準備のできた精神に訪れる。
◇セレンディピティ:何かに出会ったとき、その意味を悟り、偶然を必然とする能力が必要とされる。
◇人間の脳は自己完結しない。常に世界とさまざまな情報のやり取りをしてはじめて生き生きと脳は働くことができる。
◇人間は一生学び続ける存在。自分がぎこちないと感じるような新しいことにチャレンジし続けなければ、せっかくの脳の学習能力を生かすことはできない。
◇ヴァカンスで忘れていた自分に出会えたりする。
◇頭の中の「わからないこと」、10年も分からない問題があったら、とびっきりの研究テーマだ。
◇美は社会の未来を切り開く創造性のインフラ。
◇本当の主語は何か?主語を置き換えてみることで世界は少し違ったものに見えてくる。
◇セレンディピティという面から見ても、とにかく行動してみることは重要。
◇自分なりの直感によって情報を収集し、評価し、編集し、そして新しい価値を生み出す。

◇究極は、この上なく複雑であるとは言ってもやはり物質にすぎない脳に、いかにして「心」が宿るのかという問い。
◇疾病に即して解決への道を探る「臨床医学」があるように、一人一人の人生の中で起こった具体的な出来事に脳の視点から向き合う「臨床脳科学」があってもいい。
◇創造することは思い出すことに似ている
◇情報は外からやってくるだけでなく、自分の中から掘り起こすものでもある。
◇一度過ぎ去ったことは変える事はできないけれれど、過去の見方を変える事はできる年をとると言うことは、記憶の「編集力」を通して新たな発見をなし得る、豊かな可能性の鉱脈がそれだけ増えるということ。
◇脳も一つの生きた臓器である以上、その健康に気を配るのは当然。本を読むこと、それは一つの手入れである。
◇感情の役割は、生きていく中で直面する不確実さにうまく対応することである。
◇進化の過程で残った感情は、生きるための意味を持っている。
◇科学は、仮説を立て、それを検証することで進歩していく。
◇鏡は自分をあたかも他人であるかのように見る道具である。
◇私たちは生活の状況にあわせて少しずつ違う人格が現れる。マイルドな多重人格者とも言える。
◇不安や恐怖、嫉妬といったネガティブな気持ちも、感情のエコロジーの中で果たすべき役割があるからこそ、進化の過程で生き残った。
◇さまざまな人生経験を通じて、感情のエコロジーの多様性を耕していくことが大事。
◇外から興味深い刺激が入ってこない状態で、脳が自ら何かを作り出そうとするときに、ひらめきが訪れるらしい。
◇動物は「安全基地を確保する」という命題と「新しい可能性を探求する」という命題を両立させることで生き延びてきた。
◇人間の判断はルールでは書けない。
◇「サッカー型」の組織を維持する上では「言葉」の役割が大きい。トップが明確なメッセージを出し続けることが、個人の自発性が組織の中で生かされ、組織のパフォーマンスが上がるための条件といえる。
◇人間は他者という鏡を得てはじめて自己を磨くことが出来るし、ユニークな個性をはぐくむことも出来る。
◇言葉とは他人と自分とを結ぶ「鏡」のシステムの産物。
◇幸運は準備のできた精神に訪れる。
◇セレンディピティ:何かに出会ったとき、その意味を悟り、偶然を必然とする能力が必要とされる。
◇人間の脳は自己完結しない。常に世界とさまざまな情報のやり取りをしてはじめて生き生きと脳は働くことができる。
◇人間は一生学び続ける存在。自分がぎこちないと感じるような新しいことにチャレンジし続けなければ、せっかくの脳の学習能力を生かすことはできない。
◇ヴァカンスで忘れていた自分に出会えたりする。
◇頭の中の「わからないこと」、10年も分からない問題があったら、とびっきりの研究テーマだ。
◇美は社会の未来を切り開く創造性のインフラ。
◇本当の主語は何か?主語を置き換えてみることで世界は少し違ったものに見えてくる。
◇セレンディピティという面から見ても、とにかく行動してみることは重要。
◇自分なりの直感によって情報を収集し、評価し、編集し、そして新しい価値を生み出す。

Posted by 茶花スタッフ at 14:46│Comments(1)
この記事へのコメント
ビジネス書・・・読んでますねぇ!
いわゆる「経済評論家」が語る理想論とは違って
実務経験者の語る言葉というのは実に含蓄溢れるものです。
かく言う私も平成6年9月に起業して、13年近く何とか食ってますが、
この13年の軌跡で見ると、己の実力(意欲?)の無さがよくわかります。
経営って難しいですなぁ・・・楽しいけど(笑)
そういう意味で、貴殿の行動力と実行力には
親しい友人として日頃から敬愛してやまないものがあります。
近いうち、島菜でメシでもご一緒しましょう♪
Posted by いのけん at 2007年02月27日 08:49