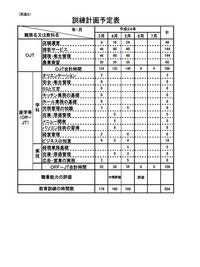› 仕事は芸術だ! › サービス・ストラテジー
› 仕事は芸術だ! › サービス・ストラテジー2007年05月01日
サービス・ストラテジー
価値優位性のポジショニング
サービス・ストラテジー 著)ジェームスズ・トゥボール
◇製品はサービスを形にしたもの、という見方もできる。自動車は快適な移動を可能にし、テレビはエンターテイメントを届ける。
◇顧客を引きつけるのは性能だが、購入を決定付けるのはサービスである。
◇製品や情報との関連が薄いサービスは生産性向上の余地は小さい。
◇サービスは、生産と消費が同時に起きているため、無形性を大きな特徴とする。モノとは違い、店頭に並べるわけにもいかず、所有や買取もできない。特許による保護も不可能である。サービスの中身や効用を伝えるのには往々にして実例を示すしかない。すなわち記憶に残るサービスが有効となる。
◇顧客はサービスを実現するために欠かせない存在であり、その果たす役割は大きい。また、顧客はサービス提供者を導き、管理する役割も担う。
◇顧客参加のもとでサービスを提供すると、不確実性につながるのも確かだが、よろよいサービスを実現する上では欠かせない条件でもある。その意味でも顧客はパートタイム従業員、あるいはサービスの共創者のような役割を果たしている。
◇サービスは、顧客の求めに応じてその場で生み出すものであるため、所有や収集ができず、生み出されるそばから消費するほかない。顧客に提供されるまさにその場所以外には存在しようが無い。
◇生産性の向上余地の少ないサービス業においては稼働率をかぎりなく100%に近づけることが重要となる。
◇サービスは、顧客の目の前でそのとき限りで提供するものであるため、一度で満足のいく成果をあげなくてはならない。
◇顧客と接する数秒~数分間の「真実の瞬間」こそが、めぐりめぐってサービス企業の盛衰を決める。
◇形あるモノの販売促進は通常メディアをとおして行われるが、サービスの販促には、そのサービスを実際に経験した顧客による口コミのほうが効果的である。
◇なによりもまず最終顧客の視点に立ち、顧客の求める価値を生み出すよう勤めるべきである。
◇サービス・ミックス:製品(Product)、価格(Price)、販売促進(Promotion)、場所(Place)、+プロセス(Process)、人(People)
◇顧客は何にも増して、なじみぶかいシステムや見知った顔と接することを好む。一人一人の顧客との繋がりをより確かなものしに、具体的な顧客ニーズに添うよう努力すれば、サービス企業は参入障壁を築き、強気の価格を貫ける。
◇それにより、範囲の経済(従来よりも広いサービスを利用してもらうクロスセリング)あるいは関係性の経済(頻繁に利用してもらう)の効果がある。
◇サービスの販促には従業員の尽力が欠かせない。したがって、サービスの提供に携わる人材にそのサービスの素晴らしさを説く必要がある。これが社内マーケティングである。これにはメーカーが流通網に傾けるのと同じくらい注意を払うべきである。
◇サービスの本当の価値を示し、顧客に届けるのはもとより、サービス経験を顧客にとって忘れがたいものにするのは、あくまでも最前線のスタッフである。
◇大切なのは結果や成果であり、顧客がどれだけ価値を認識したかなにだ。
◇「お客様に接するときと同じように従業員にも接しよう」という標語は、顧客と従業員が共に価値を生み出すプロセスにかかわっているという事実を踏まえたものだ。
◇顧客はサービスの創造に自ら参加し、カスタマイゼーションを行い、サービス全体をまとめあげる役割を担う。
◇サービスが重視されればされるほど、軸足は取引そのものから関係性に移り、サービスミックスの重要性が高まる。
◇サービスの提供に伴う顧客とのやりとりが最高のコミニケーションである。
◇評価ギャップ=印象-期待
◇企業が顧客を失うのは、多くの場合、従業員が顧客に十分な感心を示さないのが原因である。
◇状況の法則:人は置かれた状況の意味を自分なりにつかんだときはじめて他人の指示に従う。

サービス・ストラテジー 著)ジェームスズ・トゥボール
◇製品はサービスを形にしたもの、という見方もできる。自動車は快適な移動を可能にし、テレビはエンターテイメントを届ける。
◇顧客を引きつけるのは性能だが、購入を決定付けるのはサービスである。
◇製品や情報との関連が薄いサービスは生産性向上の余地は小さい。
◇サービスは、生産と消費が同時に起きているため、無形性を大きな特徴とする。モノとは違い、店頭に並べるわけにもいかず、所有や買取もできない。特許による保護も不可能である。サービスの中身や効用を伝えるのには往々にして実例を示すしかない。すなわち記憶に残るサービスが有効となる。
◇顧客はサービスを実現するために欠かせない存在であり、その果たす役割は大きい。また、顧客はサービス提供者を導き、管理する役割も担う。
◇顧客参加のもとでサービスを提供すると、不確実性につながるのも確かだが、よろよいサービスを実現する上では欠かせない条件でもある。その意味でも顧客はパートタイム従業員、あるいはサービスの共創者のような役割を果たしている。
◇サービスは、顧客の求めに応じてその場で生み出すものであるため、所有や収集ができず、生み出されるそばから消費するほかない。顧客に提供されるまさにその場所以外には存在しようが無い。
◇生産性の向上余地の少ないサービス業においては稼働率をかぎりなく100%に近づけることが重要となる。
◇サービスは、顧客の目の前でそのとき限りで提供するものであるため、一度で満足のいく成果をあげなくてはならない。
◇顧客と接する数秒~数分間の「真実の瞬間」こそが、めぐりめぐってサービス企業の盛衰を決める。
◇形あるモノの販売促進は通常メディアをとおして行われるが、サービスの販促には、そのサービスを実際に経験した顧客による口コミのほうが効果的である。
◇なによりもまず最終顧客の視点に立ち、顧客の求める価値を生み出すよう勤めるべきである。
◇サービス・ミックス:製品(Product)、価格(Price)、販売促進(Promotion)、場所(Place)、+プロセス(Process)、人(People)
◇顧客は何にも増して、なじみぶかいシステムや見知った顔と接することを好む。一人一人の顧客との繋がりをより確かなものしに、具体的な顧客ニーズに添うよう努力すれば、サービス企業は参入障壁を築き、強気の価格を貫ける。
◇それにより、範囲の経済(従来よりも広いサービスを利用してもらうクロスセリング)あるいは関係性の経済(頻繁に利用してもらう)の効果がある。
◇サービスの販促には従業員の尽力が欠かせない。したがって、サービスの提供に携わる人材にそのサービスの素晴らしさを説く必要がある。これが社内マーケティングである。これにはメーカーが流通網に傾けるのと同じくらい注意を払うべきである。
◇サービスの本当の価値を示し、顧客に届けるのはもとより、サービス経験を顧客にとって忘れがたいものにするのは、あくまでも最前線のスタッフである。
◇大切なのは結果や成果であり、顧客がどれだけ価値を認識したかなにだ。
◇「お客様に接するときと同じように従業員にも接しよう」という標語は、顧客と従業員が共に価値を生み出すプロセスにかかわっているという事実を踏まえたものだ。
◇顧客はサービスの創造に自ら参加し、カスタマイゼーションを行い、サービス全体をまとめあげる役割を担う。
◇サービスが重視されればされるほど、軸足は取引そのものから関係性に移り、サービスミックスの重要性が高まる。
◇サービスの提供に伴う顧客とのやりとりが最高のコミニケーションである。
◇評価ギャップ=印象-期待
◇企業が顧客を失うのは、多くの場合、従業員が顧客に十分な感心を示さないのが原因である。
◇状況の法則:人は置かれた状況の意味を自分なりにつかんだときはじめて他人の指示に従う。

Posted by 茶花スタッフ at 16:26│Comments(0)