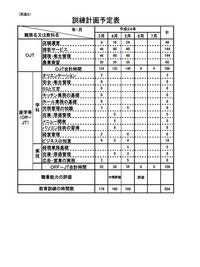› 仕事は芸術だ! › ドラッガーの遺言
› 仕事は芸術だ! › ドラッガーの遺言2007年07月03日
ドラッガーの遺言
ドラッガーの遺言 著)ピーター・F・ドラッガー
◇真にグローバル化をなし得るものは、ただ一つ、「情報」のみである。
◇グローバリゼーションについて語っている時、人は情報について語っている。
◇グローバルバル化した情報へのアクセスをスムースにする英語力は非常に大きな武器。
◇「権力」ではなく、グローバル化した「情報」によって世界が強固に結びつく。
◇「金融を基盤とした世界経済」から「情報を基盤とした世界経済」へ。
◇現代の国際競争において意味を持つのは唯一、「知識労働における生産性」のみである。
◇いかに効率的に経営できるか戦略を練り、研究・開発をコントロールしていくかに知恵を絞る頭脳労働=知識労働が、その中心をなしている。
◇事業計画を立案し、設計やデザインを考え、マーケティングや研究開発に知恵を絞ること、そして自ら手がける必要のないものを選別してアウトソーシングすること。すなわち、「戦略」を管理する経営構造の確立こそ、知識労働時代の最も重要な課題である。
◇専門知識を有する知識労働者を集団にし、チームとして機能させることが、生産性を高めるために必要不可欠。
◇知識社会においては、知識を生産的にすることが競争を可能にするただ一つの方策。
◇何を残し、何を変えていくのか。この舵取りを誤ったならば、日本社会は早晩、時代の変化についていけなくなる。
◇「問題重視型」の思考に囚われるな。「機会重視型」の発想をもて。
◇変化は予想できず、理解することも困難で、みなが考える常識に反する形で起こる。しかし、変化に考えをすり合わせていく過程こそ、好機は訪れる。
◇現実における変化は、決して以前のものとは同じにならない。そして、机上で考える変化より先に現れる。
◇「成果を得るためには、どんな強みを活かして、何をしなければならないのか?」経営の本質は、すべてこのひと言に表されています。
◇「目的は何で、その達成のために何をすべきか」
◇生まれついてのリーダーなど存在せず、リーダーとして効果的にふるまえるような習慣を持つ人が、結果としてリーダーへと育つ。
◇有能なリーダーはまず「何をする必要があるか」を問う。
◇不得手なことには、決して自ら手がけない。
◇部下とコミニケーションを取ることを自らの責任と捉えている。
◇決定とは「将来に対する現時点でのコミットメント」
◇長所を探り出し、それを確立し、発展させていくこと、それをキャリアのできるだけ早い段階から始めること。
◇弱みを知ること=何をすべきでないかを知ることは、自らをイノベートしていく際の第一歩。
◇「今何を捨て、何を選択し、自己を高めるために何を学ぶべきか」を絶えず問い続ける姿勢こそ、個人のイノベーションを促進する。

◇真にグローバル化をなし得るものは、ただ一つ、「情報」のみである。
◇グローバリゼーションについて語っている時、人は情報について語っている。
◇グローバルバル化した情報へのアクセスをスムースにする英語力は非常に大きな武器。
◇「権力」ではなく、グローバル化した「情報」によって世界が強固に結びつく。
◇「金融を基盤とした世界経済」から「情報を基盤とした世界経済」へ。
◇現代の国際競争において意味を持つのは唯一、「知識労働における生産性」のみである。
◇いかに効率的に経営できるか戦略を練り、研究・開発をコントロールしていくかに知恵を絞る頭脳労働=知識労働が、その中心をなしている。
◇事業計画を立案し、設計やデザインを考え、マーケティングや研究開発に知恵を絞ること、そして自ら手がける必要のないものを選別してアウトソーシングすること。すなわち、「戦略」を管理する経営構造の確立こそ、知識労働時代の最も重要な課題である。
◇専門知識を有する知識労働者を集団にし、チームとして機能させることが、生産性を高めるために必要不可欠。
◇知識社会においては、知識を生産的にすることが競争を可能にするただ一つの方策。
◇何を残し、何を変えていくのか。この舵取りを誤ったならば、日本社会は早晩、時代の変化についていけなくなる。
◇「問題重視型」の思考に囚われるな。「機会重視型」の発想をもて。
◇変化は予想できず、理解することも困難で、みなが考える常識に反する形で起こる。しかし、変化に考えをすり合わせていく過程こそ、好機は訪れる。
◇現実における変化は、決して以前のものとは同じにならない。そして、机上で考える変化より先に現れる。
◇「成果を得るためには、どんな強みを活かして、何をしなければならないのか?」経営の本質は、すべてこのひと言に表されています。
◇「目的は何で、その達成のために何をすべきか」
◇生まれついてのリーダーなど存在せず、リーダーとして効果的にふるまえるような習慣を持つ人が、結果としてリーダーへと育つ。
◇有能なリーダーはまず「何をする必要があるか」を問う。
◇不得手なことには、決して自ら手がけない。
◇部下とコミニケーションを取ることを自らの責任と捉えている。
◇決定とは「将来に対する現時点でのコミットメント」
◇長所を探り出し、それを確立し、発展させていくこと、それをキャリアのできるだけ早い段階から始めること。
◇弱みを知ること=何をすべきでないかを知ることは、自らをイノベートしていく際の第一歩。
◇「今何を捨て、何を選択し、自己を高めるために何を学ぶべきか」を絶えず問い続ける姿勢こそ、個人のイノベーションを促進する。

Posted by 茶花スタッフ at 18:53│Comments(0)